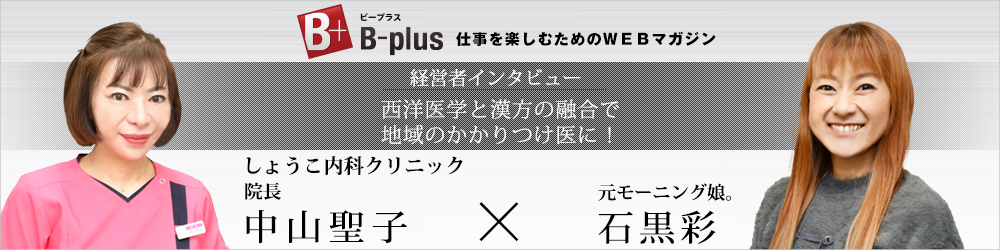お知らせ

【医療コラム】季節の変わり目に風邪をひく理由と免疫を守る3つの予防習慣を解説

季節の変わり目に体調を崩したことがある方は多いのではないでしょうか。朝晩と日中の寒暖差や、気圧の変化は、私たち自身の力ではコントロールしにくい環境ストレスです。
こうした環境ストレスは自律神経の乱れを招き、体調を崩す原因になりますが、正しい予防法を実践することで、そのリスクを減らすことができます。そこで本記事では、季節の変わり目に風邪をひきやすい理由を解説し、免疫力を高めるために重要な3つの予防習慣をご紹介します。季節の変わり目に体調を崩しやすい方は、ぜひ参考にしてみてください。
季節の変わり目に風邪をひきやすい理由
季節の変わり目は、一日の中で気温差や気圧の変動が大きいだけでなく、日によって寒かったり暖かかったりします。この変化は、体の様々な機能を司る自律神経にとって大きなストレスとなります。
自律神経には、活動時に優位に働く交感神経と、リラックス・休息時に優位に働く副交感神経があり、それぞれがバランスをとりながら体をコントロールしています。ところが、寒暖差や気圧の変化で自律神経のバランスが乱れると、免疫機能に対して次の変化が起こりやすくなります。
1.免疫細胞の働きが鈍くなる
自律神経が乱れると、血管の収縮・拡張のコントロールがうまくいかなくなり、血流が悪くなります。血液は酸素や栄養だけでなく、免疫細胞を運ぶ役割も担っています。血流が悪化すると、免疫細胞の一つである白血球の働きが鈍くなって病原体を攻撃しにくくなります。
また、血流の悪化は冷えを招きます。一般に、体温の低下は免疫細胞の活動を鈍らせると考えられており、その目安として、体温が1℃下がると免疫力は30%低下するとも言われています。つまり、血流の悪化による冷えは、風邪の大きな原因となります。
2.ストレスホルモンが免疫細胞を抑制する
交感神経が過剰に働くと、副腎からストレスホルモン(コルチゾールなど)が分泌されます。このホルモンは、病原体を攻撃するリンパ球(T細胞、NK細胞など)の働きを抑制してしまう作用があり、体の防御機能が低下します。さらに、ストレスによる自律神経の乱れは、副交感神経の働きをも弱めてしまいます。すると、リンパ球が活性化しにくくなるため、免疫力が低下します。
このように、自律神経の乱れは免疫機能を低下させ、体の抵抗力を弱めます。季節の変わり目に風邪をひきやすい方や、慢性的な冷えに悩まされている方は、自律神経のバランスを回復させることが、根本的な対策となります。

季節の変わり目に風邪をひかないための「3つの予防習慣」
季節の変わり目の風邪を防ぐには、乱れがちな自律神経のバランスを整え、免疫力を維持することがとても重要です。特に環境ストレスで、交感神経が高ぶりがちなため、リラックス時に優位になる副交感神経の働きを高めることが、風邪予防のカギとなります。そこで、自律神経と免疫に直結する「睡眠」「食事」「冷え対策」の3つの習慣を詳しく解説します。
〇睡眠
睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、自律神経と免疫機能にとって最も重要なメンテナンスの時間です。睡眠中は副交感神経が優位になり、全身がリラックスすることで体の修復が促され、免疫細胞が活性化します。
良質な睡眠をとるために、以下のことを意識しましょう。
1.規則的な睡眠で体内時計を整える
不規則な生活は自律神経を大きく乱します。夜間に活動しすぎたり、昼夜逆転したりする生活は、免疫力を低下させるストレスホルモンの分泌を増やし、免疫細胞の働きを抑制してしまいます。
そうならないために、毎日決まった時間に起きて朝の光を浴び、体内時計を整えましょう。体内時計が整うと、夜間に副交感神経が優位になりやすくなります。
2.寝る前はリラックス習慣を取り入れる
スマートフォンやパソコンのブルーライトは交感神経を刺激し、睡眠の質を低下させます。就寝前の使用は避けましょう。また、入眠の1時間前には間接照明などを使い、アロマや読書、軽いストレッチなど、自分なりのリラックス方法で心身を休ませることが大切です。

〇食事
食事は免疫細胞そのものの材料となり、また免疫の司令塔である腸内環境を整える役割を担います。バランスのとれた食事が基本ですが、次のことも心がけてみましょう。
1.朝食を食べる
朝食を食べると、体内時計が整いやすくなります。忙しさなどを理由に摂らない人もいますが、朝食は自律神経の乱れを防ぐ上で、とても大切な習慣です。
2.腸活で免疫力の土台を築く
免疫細胞の約7割が集中する腸の環境を整えるため、発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)や食物繊維を積極的に摂りましょう。腸内細菌がバランスよく働くことで、免疫力が安定的に維持されます。
3.免疫細胞の材料をしっかり摂る
自律神経を機能させる神経伝達物質や免疫細胞を作るために、質の良いタンパク質(肉、魚、豆類)は欠かせません。また、ビタミン(特にA、C、E)やミネラル(亜鉛など)は免疫細胞の働きをサポートします。これらの栄養素を含む緑黄色野菜やきのこ、海藻類をバランスよく摂りましょう。
〇冷え対策
風邪をよせつけない体づくりには、冷え対策も重要です。
1.ぬるめのお湯で入浴し、自律神経を整える
入浴は、自律神経のバランスを整える最も手軽で効果的な方法の一つです。熱いお風呂は交感神経を刺激してしまうため、38~40℃程度のぬるめのお湯に、15分ほどかけてゆっくり浸かりましょう。ぬるめのお湯にゆっくり浸かると、血行も良くなるため、冷えの改善にも効果的です。
2.寒暖差対策で体温を安定させる
朝晩と日中の寒暖差が激しい日は、自律神経が体温調節に過剰に働くため、疲弊します。カーディガンやストールなど、すぐに脱ぎ着できる上着を活用し、特に皮膚が薄く血管が近い三首(首元、手首、足首)を冷やさないように心がけましょう。
その他にストレス発散も重要です。ストレスがたまると交感神経が優位になりやすく、自律神経のバランスが乱れます。好きなことをしたり、リラックスする時間をとって、副交感神経の活動を高めましょう。
このような自律神経を整える習慣を取り入れながら、手洗い・うがいといった基本的な感染症対策をしっかり行うことで、風邪のリスクをぐっと減らすことができます。

季節の変わり目の不調や風邪、内科受診の目安とは
セルフケアで風邪を予防することは大切ですが、症状が長引いたり悪化したりする場合は、自己判断せずに内科で適切な診断と治療を受けましょう。とくに以下のような症状が見られる場合は、受診をおすすめします。
- 発熱(37.5℃以上)が2日以上続く、または急な高熱が出た
- 咳がひどく、呼吸が苦しい、胸の痛みを伴う
- 水分が摂れず、脱水症状の兆候がある
- 異常な倦怠感があり、日常生活に支障が出ている
- 市販薬を飲んでも症状が改善せず、むしろ悪化している
- 喉の痛みが非常に強く、扁桃腺の腫れがひかない
最初は風邪でも、それをきっかけに気管支炎や肺炎、副鼻腔炎を合併してしまうケースも少なくありません。また、風邪だと思っていても、実は別の病気が影響している可能性もあります。特に高齢者や持病がある方は早めに受診しましょう。

まとめ
季節の変わり目は、誰にとっても体調を崩しやすい時期です。自律神経を整える習慣を取り入れて、免疫力を高めましょう。
そして、風邪をはじめとする感染症は内科の専門分野です。風邪を繰り返す方や不調が長引く方は、無理をせず内科を受診しましょう。
記事の要点
- 季節の変わり目の風邪は、寒暖差による自律神経の乱れが原因。
- 自律神経の乱れは、免疫細胞の働きを抑制し、冷えを招いて抵抗力を弱める。
- 予防には、良質な睡眠、バランスの取れた食事、適切な冷え対策の3つの習慣が重要。
- 高熱が続く、咳が止まらないなど症状が悪化する場合は内科医に相談を。
当クリニックにおける内科診療のご案内 はこちらよりご覧くださいませ。